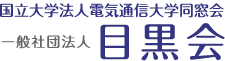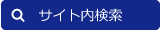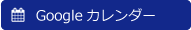今年のスマートテクノロジーフォーラム(STF)は、より多くの方に気軽にご参加いただけるよう、昨年に引き続き対面とオンラインによるハイブリッド開催といたしました。
「AIが変える社会~挑むべき課題と描く未来~」というテーマで、2025年9月26日(金)14時に予定通り開催し、対面参加約40名、オンライン参加約60名、合計約100名の方々にご参加いただきました。
盛況のうちに終了することができましたことを、講演者の皆様、参加いただいた皆様に御礼申し上げます。
 フォーラムは、まず司会の上田敏樹目黒会学術講演委員会委員長から本フォーラムの開催趣旨、講演内容の説明のあと、「AIが変える社会~挑むべき課題と描く未来~」をテーマに東京科学大学特任教授 市川類氏、日本アニメフィルム文化連盟事務局長 福宮あやの氏、東京学芸大学教授 森本康彦氏、電気通信大学教授 伊藤 毅志氏の4名の講演者にご講演いただきました。
フォーラムは、まず司会の上田敏樹目黒会学術講演委員会委員長から本フォーラムの開催趣旨、講演内容の説明のあと、「AIが変える社会~挑むべき課題と描く未来~」をテーマに東京科学大学特任教授 市川類氏、日本アニメフィルム文化連盟事務局長 福宮あやの氏、東京学芸大学教授 森本康彦氏、電気通信大学教授 伊藤 毅志氏の4名の講演者にご講演いただきました。
 最初に講演1では市川氏から「世界と日本のAI規制・ガバナンス政策を巡る最近の動向」と題して、世界と日本のAI規制・ガバナンス政策を巡る最新の動向についてお話いただきました。最初に、AI規制・ガバナンスの枠組みについて、特にAI技術は将来的不安感から規制を行なう動きがあることが特徴であり、文化的な要因により地域差があることからAI規制・ガバナンス政策は多様性があることを説明いただきました。欧米各国が最先端AIモデルの規制強化の方向に進むが、2025年に入ってから一転し、世界各国ともAIイノベーションの推進の方向に舵を切る話がありました。米国・欧州・中国の対立する動きの中で日本は中立的な役割を果たしていることが話されました。
最初に講演1では市川氏から「世界と日本のAI規制・ガバナンス政策を巡る最近の動向」と題して、世界と日本のAI規制・ガバナンス政策を巡る最新の動向についてお話いただきました。最初に、AI規制・ガバナンスの枠組みについて、特にAI技術は将来的不安感から規制を行なう動きがあることが特徴であり、文化的な要因により地域差があることからAI規制・ガバナンス政策は多様性があることを説明いただきました。欧米各国が最先端AIモデルの規制強化の方向に進むが、2025年に入ってから一転し、世界各国ともAIイノベーションの推進の方向に舵を切る話がありました。米国・欧州・中国の対立する動きの中で日本は中立的な役割を果たしていることが話されました。
 講演2では、福宮氏から「AnimateとGenerateー著作権の現在地ー」と題し、最初に生成AIと著作権について国内および海外での現状が話されました。次にアニメの制作工程をキャラクターデザインからビデオ編集まで具体的な作業の説明をいただきました。続けて著作権の所在が生成AI以前から多大な問題をかかえていること、アニメ業界の収入格差など、厳しい現状に置かれていることなどの話があり、最後に日本のアニメがなぜ世界に評価されるのかの話がありました。
講演2では、福宮氏から「AnimateとGenerateー著作権の現在地ー」と題し、最初に生成AIと著作権について国内および海外での現状が話されました。次にアニメの制作工程をキャラクターデザインからビデオ編集まで具体的な作業の説明をいただきました。続けて著作権の所在が生成AI以前から多大な問題をかかえていること、アニメ業界の収入格差など、厳しい現状に置かれていることなどの話があり、最後に日本のアニメがなぜ世界に評価されるのかの話がありました。

講演3では、森本氏から「初等中等教育における生成AIの活用」と題し、文部科学省が2024年に「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドラインVer2.0」を公開したことで生成AIの適切でない活用例、適切である活用例の指針が示され、児童生徒が生成AIを活用するための鍵は主体性と学び方にあることが話されました。続けて小学校高学年の総合学習の様子を紹介され、生成AIを「仲間」として活用したり、「先生・先輩」として活用したり、具体的に紹介いただきました。最後に生成AIを活用した学びの4ヶ条(学習者が主体的であることなど)のお話をしていただきました。

講演4では、伊藤氏から「ゲームAI研究の進化と展望」と題し、チェスや将棋、囲碁といった思考ゲームはルールが明確で勝敗が定量化できるため、人工知能の評価に適した題材として研究されてきたことが紹介されました。最初にチェスAIは1997年にはDeepBlueがカスパロフを破り、膨大な探索能力が人間を凌駕することを実証しました。将棋AIでは2006年のBonanzaに代表される機械学習による評価関数自動生成が革新をもたらしました。囲碁AIでは2006年のモンテカルロ木探索の導入により大きく進展しました。ゲームAIが人間とAIの共生のあり方を考えるための優れた実験場であり続けることの話がありました。
今後も本フォーラムでは、参加者のアンケート結果を参考にして参加者の興味・関心の高いテーマを選定し、参加者に有益となる情報を提供していきたいと考えております。
次回もぜひ皆様のご参加をお待ちしております。